スペアキー作成が難しい理由と、大家さんが知っておくべき正しい依頼先
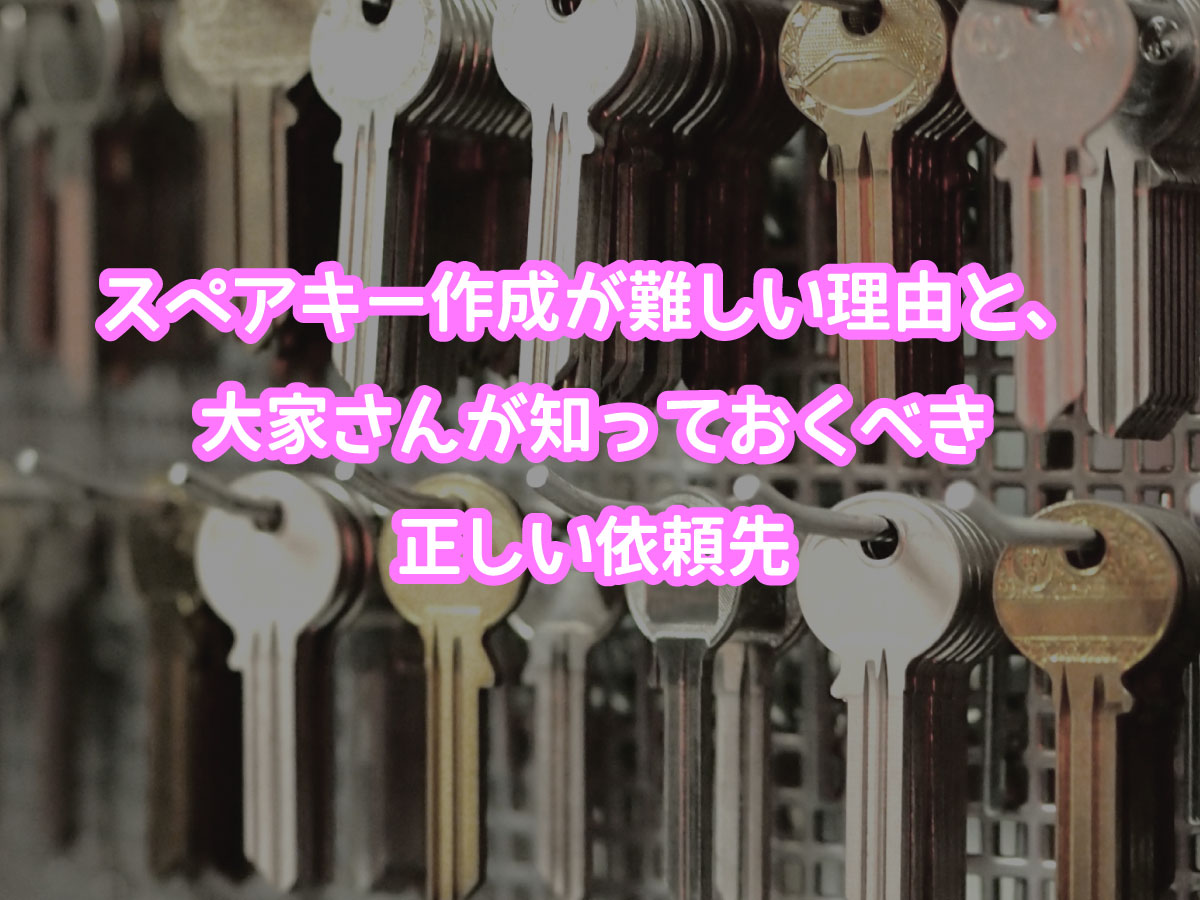
はじめに|「スペアキーくらいすぐ作れる」時代はもう終わり
「合鍵を作りたいだけなのに、断られてしまった」
そんな経験をされた大家さんやオーナーの方も多いのではないでしょうか。
昔はホームセンターや金物屋に鍵を持ち込めば、数分で合鍵を作ってもらえました。
ところが近年では、「この鍵はウチでは作れません」「メーカーへの取り寄せになります」と言われるケースが急増しています。
その理由は、鍵の防犯性能が年々高くなっているからです。
ピッキング被害が社会問題になった2000年代以降、住宅用の鍵は「簡単に複製できない」「不正に開けられない」構造へと進化しました。
一方で、これは鍵を管理する側――つまり大家さん・オーナーにとっても“新たな課題”を生むことになりました。
たとえば、入居者への鍵の引き渡しや、スペアキーの保管・再発行。
管理物件が複数ある場合、合鍵の数や保管場所を誤ると、「どの鍵がどの部屋か分からない」「紛失時の再作成に時間がかかる」など、
業務上のリスクが発生します。
さらに、防犯性の高いディンプルキーや電子キーは、メーカー登録や所有者証明が必要な場合もあり、「合鍵を作る=手続き・費用・日数がかかる」のが今の現実です。
つまり、“スペアキー作成”はもはや簡単な作業ではなく、安全性と信頼を守るための管理業務の一環と言えます。
この記事では、なぜ今スペアキー作成が難しくなっているのか、どんな種類の鍵が対応困難なのか、そして大家さん・オーナーが知っておくべき「正しい依頼先」について、防犯とコストの両面から詳しく解説します。
なぜ“スペアキーが作れない”ことが増えているのか
ホームセンターや金物屋で「この鍵は作れません」と言われることが増えたのは、単なる設備の問題ではなく、鍵そのものの仕組みと管理制度が変わったためです。
ここでは、その主な理由を3つの視点から解説します。
1. 鍵の構造が複雑化している
従来の「ギザギザ型」のピンシリンダーキーは、鍵山(ギザギザの形)を機械で削ればすぐに複製できました。
しかし現在主流のディンプルキーやマグネット式・電子式キーは、内部構造が非常に複雑で、一般的な複製機では対応できません。
また、ディンプルキーは数千通り以上のピン配置パターンを持ち、わずかなズレでも鍵穴に入らない精密構造になっています。
そのため、専門の機械や正確なデータを持つ業者でなければ、「正確に複製することができない」のです。
2. 不正複製・犯罪防止のためのセキュリティ強化
かつては、鍵に刻印された番号(例:MIWA・GOAL・WESTなど)を見れば、同じ形状のブランクキー(未加工の鍵)を入手できました。
しかし現在では、この番号を悪用した不正複製事件が増加したことから、メーカー側が鍵番号だけでの複製注文を禁止しています。
その代わりに導入されたのが「メーカー登録制」や「オーナーカード制」。
正規ルートで合鍵を作るには、所有者証明(登録証や保証書)が必要となり、登録されていない第三者が複製を依頼することはできません。
この制度により、防犯性は飛躍的に高まりましたが、オーナーにとっては「正しい手順を踏まないと作れない」という手間が増えたとも言えます。
3. 鍵のデジタル化・システム化が進んでいる
近年は、賃貸住宅やテナントビルでも電子キー・ICカードキーを導入するケースが増えています。
これらは、物理的な鍵の形状ではなくデータ情報(暗号コード)で開閉を制御するため、一般的な鍵屋やホームセンターでは複製ができません。
また、マスターキーや共用部連動キーなどのシステムキーは、建物全体で登録・管理されているため、勝手に合鍵を作るとセキュリティシステム全体に影響を及ぼす恐れがあります。
つまり、スペアキーを作るには、構造・データ・登録の3つが揃っていなければならず、「誰でも・すぐに・どこでも作れる」時代は終わったのです。
次の章では、賃貸物件を管理するオーナーが実際に直面する「スペアキーが必要になる代表的なケース」を紹介します。
スペアキーが必要になる主なケース(オーナー視点)
賃貸物件やテナントを所有するオーナーにとって、スペアキーの作成は避けて通れない日常業務のひとつです。
しかし、作成の目的によって必要な本数や依頼先、費用の目安は異なります。
ここでは、実際によくある5つのケースを見ていきましょう。
1. 新規入居者への鍵引き渡し時
入居時に新しい鍵を渡すのは当然のことですが、物件によっては入居者分・管理用・合鍵予備分など、
複数本を用意しておく必要があります。
特に防犯性の高いディンプルキーの場合、メーカー発注で1〜2週間程度かかることもあり、入居日までのスケジュール管理が重要です。
また、以前の入居者が合鍵を持っているリスクを避けるため、退去時には必ず鍵交換または登録再発行を行うようにしましょう。
2. 鍵の紛失・破損時
入居者や従業員が鍵を紛失してしまうケースは少なくありません。
その際、合鍵を1本も保管していないと、ドア開錠・鍵交換・再発行の費用がすべてオーナー負担になる場合もあります。
鍵の種類によっては1本あたり3,000〜10,000円ほどかかるため、管理用のスペアキーを常備しておくことで、緊急時の対応コストを大幅に軽減できます。
3. 清掃・点検・管理業者への一時貸与
共用部の定期清掃や、設備点検・修繕対応の際には、一時的に業者へ鍵を貸し出す場面もあります。
このような場合、複数の物件や部屋を管理していると、 「どの鍵をどの業者に貸したか分からなくなる」トラブルが起こりがちです。
スペアキーを作成する際は、物件ごとに番号やタグで識別管理し、貸与・返却履歴を残すことが重要です。
これにより、鍵紛失時の追跡や責任の所在も明確になります。
4. テナント・店舗の鍵を複数で共有したいとき
オフィスや店舗では、複数のスタッフが出入りするため、スペアキーを一定数作成しておく必要があります。
特に、複数の従業員が同じドアを利用する場合、鍵管理体制を整えないと内部トラブルの原因にもなりかねません。
マスターキーや共用キーを導入すれば、1本で複数箇所を管理でき、鍵の持ち歩き・貸し出しも効率的になります。
ただし、防犯上のリスクを考慮し、管理者以外には渡さないルールを徹底しましょう。
5. 鍵の統一・マスターキー化を検討する場合
複数棟・複数部屋を所有しているオーナーに多いのが鍵の種類がバラバラになってしまう問題です。
管理効率を上げるために、物件ごとに鍵を統一したり、マスターキーシステムへ移行することがあります。
この場合、合鍵を1本ずつ作るよりも、鍵専門業者に一括で設計・作成を依頼する方が安全でコスト効率も高くなります。
特に古い建物を順次リニューアルする際は、このタイミングで鍵システムを見直すとスムーズです。
これらのように、スペアキーの作成は単なる利便性のためだけでなく、防犯性・管理コスト・緊急対応のすべてに関わる重要な判断です。
次の章では、実際にどんな鍵の種類があり、どこまで複製が可能なのかを詳しく見ていきましょう。
鍵の種類別|スペアキー作成の難易度と費用目安
一口に「合鍵」「スペアキー」といっても、鍵の種類によって作成の難易度も費用も大きく異なります。
ここでは、賃貸物件やテナントでよく使われる鍵を中心に、代表的なタイプと費用の目安をまとめました。
| 鍵の種類 | 作成の難易度 | 費用の目安(税込) | 作成できる場所 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ピンシリンダーキー (昔ながらのギザギザ型) |
低 | 約500〜1,000円 | ホームセンター/金物屋 | 複製が容易だが、防犯性は低め。 賃貸物件では交換推奨。 |
| ディンプルキー (高防犯タイプ) |
中〜高 | 約3,000〜5,000円 | 鍵専門店/メーカー経由 | ピン配置が複雑で、正確な機械が必要。 所有者登録が必要な場合も。 |
| マグネットキー | 高 | 約4,000〜7,000円 | メーカーまたは正規代理店 | 磁力による認証で、一般的な複製機では作成不可。 メーカー専用発注が必要。 |
| 電子キー/ICカードキー | 高 | 約5,000〜10,000円 | 管理会社/メーカー対応 | データ登録制。 カード番号や入退室履歴がシステム管理されている。 |
| マスターキー・システムキー | 非常に高 | 要見積り(10,000円〜) | 鍵専門業者のみ対応 | 建物全体を統括する鍵。 勝手な複製はセキュリティ上NG。 |
このように、昔ながらのピンシリンダーは簡単に複製できますが、その分、防犯性能が低く、空き巣被害のリスクも高くなります。
逆に、防犯性の高いディンプルキーや電子キーは、メーカー認証や登録証が必要なため、作成コストと手続きの負担が増えます。
とはいえ、防犯性が高い鍵は、入居者の安心感=物件価値の維持にもつながります。
オーナーとしては、単に「安く作れる鍵」ではなく、防犯性とコストのバランスを意識して選ぶことが大切です。
次の章では、スペアキー作成時に注意すべきリスクや、やってはいけない行為について具体的に解説します。
スペアキー作成で注意すべき4つのポイント
スペアキーの作成は、単に「便利さ」だけで考えてしまうと、防犯リスクや管理トラブルにつながることがあります。
ここでは、大家さん・オーナーが特に注意すべき4つのポイントを紹介します。
1. 鍵番号(刻印)だけでネット注文しない
最近では、ネット上で「鍵番号を入力すれば合鍵を郵送します」というサイトも見かけます。
しかし、これは非常に危険な行為です。
鍵番号はその鍵の“設計図”のようなもので、第三者が悪用すれば簡単に合鍵を作ることができてしまいます。
特に賃貸物件の場合、入居者や業者など複数の人が関わるため、鍵番号の取り扱いは厳重に管理する必要があります。
ネット注文を行う際は、必ずメーカー公式または正規登録業者を利用しましょう。
2. メーカー登録が必要な鍵は正規ルートで依頼する
防犯性の高いディンプルキーやマグネットキーの多くは、メーカーによる「所有者登録制」が導入されています。
スペアキーを作る際には、登録カード・保証書・契約者情報の提示が必要になるケースもあります。
こうした鍵を、登録なしで複製しようとする業者は信頼できません。
もし作成できたとしても、正規保証の対象外になり、後々のトラブル(開かない・不具合など)の原因にもなります。
必ずメーカー正規ルートで依頼しましょう。
3. 鍵の貸与・返却を記録する「管理台帳」をつける
スペアキーを管理するうえで欠かせないのが、鍵管理台帳です。
どの物件に、いつ、誰へ、何本貸与したのか―― これを明確にしておくことで、紛失時の追跡・責任の所在をすぐに確認できます。
特に複数棟・複数物件を所有しているオーナーの場合、「どの鍵がどこにあるかわからない」という状況は致命的です。
エクセルや専用アプリで一覧化しておくと、防犯と業務効率の両面で大きな効果があります。
4. 業者を「価格」だけで選ばない
スペアキー作成の費用は、業者によって大きく異なります。
中には「格安・即日対応」をうたう業者もありますが、正規部材を使用していない場合や、
精度の低い複製でドアが開かなくなるリスクもあります。
鍵は防犯の最前線。
価格よりも正確性と信頼性を重視し、説明が丁寧でアフターフォローのある業者を選びましょう。
特に法人契約や複数物件の管理を依頼する際は、対応品質の一貫性も重要なチェックポイントです。
これら4つのポイントを守ることで、
スペアキー作成にまつわるトラブルや情報漏えいを未然に防げます。
次の章では、複数物件を所有するオーナーが知っておくべき、効率的で安全な鍵の運用方法を紹介します。
賃貸オーナー・管理者が実践すべき鍵運用の工夫
スペアキーの管理は「作ること」よりも「どう運用するか」が重要です。
防犯性を保ちながら、効率的に物件を管理するためには、日常的なルールづくりと仕組み化が欠かせません。
ここでは、賃貸オーナー・管理者がすぐに実践できる鍵運用の工夫を紹介します。
1. 鍵ごとに管理台帳を作成する
鍵の所在を明確にする基本は、やはり台帳管理です。
物件名・部屋番号・鍵番号・作成日・貸与先・返却日を一覧化し、必要に応じてスペアキーの有無や保管場所も記録しておきましょう。
紙のノートではなく、Excelやスプレッドシートなどデジタル管理にすると、担当者間の共有がスムーズになります。
管理物件が増えても、更新・検索が簡単に行えるのがメリットです。
2. メーカー登録・シリアル管理を活用する
防犯性能の高い鍵(例:MIWA、GOAL、WESTなど)は、メーカー登録による所有者証明カードが付属している場合があります。
このカードを保管しておくことで、正規ルートでの合鍵作成や、万が一のトラブル対応がスムーズになります。
特に複数物件を所有している場合、メーカーや型番・登録番号を物件ごとに一覧化しておくと、鍵の種類や発注先を誤るリスクを防げます。
3. 入居者変更時は「鍵の再登録」または「交換」を徹底する
退去後に同じ鍵を使い回すのは、最も避けたいリスクです。
「前の入居者が合鍵を持っていた」というだけで、防犯面だけでなく管理会社・オーナーへの信頼も損なわれてしまいます。
入居者変更時には必ず、
・メーカー登録型の場合 → 再登録申請
・一般的な鍵の場合 → 鍵交換または再発行
を行うようにしましょう。
この運用をルール化しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、入居者にも安心してもらえます。
4. 鍵の種類を統一・マスターキー化して管理効率を上げる
管理物件が増えると、「どの物件にどの鍵が合うのか」が分からなくなりがちです。
この課題を解決するのが、鍵の統一化・マスターキー化です。
例えば、建物全体を同じメーカー・シリーズの鍵に揃えることで、部品交換やスペアキー作成もスムーズになります。
さらに、マスターキーを導入すれば、1本の鍵で複数の部屋を開けられるようになり、
点検・清掃時の作業効率が大幅にアップします。
ただし、マスターキーの管理は慎重に。
管理者のみが保持し、記録台帳で厳格に管理することが重要です。
5. 鍵の電子化・スマートロック導入も検討する
近年は、暗証番号式やICカード・スマートロックなど、物理的な鍵を持たない管理方法も普及しています。
スマートロックを導入すれば、鍵の受け渡しや紛失リスクを大幅に軽減できるほか、入居者の変更にも柔軟に対応できます。
初期費用はかかりますが、
長期的には管理コストの削減・セキュリティの強化につながります。
複数棟を所有しているオーナーほど、検討する価値があります。
これらの運用を取り入れることで、
スペアキー管理が「リスク」から「信頼の証」へと変わります。
次の章では、実際に鍵専門業者へ依頼する際の注意点や、費用感について解説します。
鍵専門業者に依頼するメリットと選び方
鍵の種類が多様化・高性能化する中で、ホームセンターや金物屋では対応できないケースが増えています。
そんなとき頼りになるのが、鍵専門業者(鍵屋)です。
ここでは、オーナーが知っておくべき依頼のメリットと、信頼できる業者を選ぶためのポイントを紹介します。
1. 専門知識と正確な技術による「確実な複製」
防犯性の高いディンプルキーや電子キーは、精密な加工技術と専用の複製機がなければ正確に作成できません。
鍵専門業者はメーカーごとの仕様を熟知しており、鍵の内部構造や登録情報をもとに正確なスペアキーを作成できます。
ホームセンターで「作れません」と断られた鍵でも、正規データを扱える専門業者なら対応できる場合があります。
また、メーカー登録型の鍵についても、必要な書類や手続きのサポートを受けられる点が大きな安心材料です。
2. 防犯性能の診断と総合的な提案が受けられる
スペアキーの作成だけでなく、鍵専門業者はドア全体の防犯性能を診断し、最適な対策を提案できます。
例えば、「この鍵は古く、ピッキングに弱い」「補助錠を追加した方がいい」といった現場に即したアドバイスをもらえるのは、専門業者ならではの強みです。
鍵交換・補助錠の取付・ドアクローザーの調整など、建物全体のセキュリティ向上につながる工事もまとめて依頼できます。
複数物件を所有しているオーナーにとって、一括管理できるパートナーを持つことは大きなメリットです。
3. 現場対応が早く、トラブル時にも頼れる
入居者が鍵を紛失した、開かない――そんな緊急時にも、地域密着型の鍵業者なら現場まで迅速に駆けつけ対応してくれます。
事前に信頼できる業者と契約しておくことで、緊急対応時の連絡や費用精算もスムーズになります。
また、合鍵作成や鍵交換の際に現地確認を行うことで、建物構造や防犯レベルに合わせた最適な施工が可能です。
現場を見ずに判断する業者よりも、安心感と確実性が違います。
4. 費用の目安と、業者選びで注意すべき点
スペアキーの作成費用は、鍵の種類や作業内容によって異なりますが、おおよその目安は以下のとおりです。
- ピンシリンダーキー:500〜1,000円
- ディンプルキー:3,000〜5,000円
- 電子キー・ICキー:5,000〜10,000円前後
- マスターキー・特殊キー:要見積り(10,000円〜)
費用だけで判断せず、以下のポイントも確認しましょう。
- 正規メーカー対応か(MIWA・GOAL・WESTなど)
- 防犯設備士や鍵施工技術の専門スタッフが在籍しているか
- 見積もり内容が明確で、追加費用の説明があるか
- 地域密着型で、アフター対応や保証がしっかりしているか
これらを満たす業者なら、鍵交換・修理・防犯診断まで長期的なパートナーとして信頼できます。
5. 鍵専門業者「レスキューサービス24」に依頼する場合
レスキューサービス24では、一般住宅からマンション・テナント・工場まで、さまざまな鍵の作成・交換・修理・防犯設備設置に対応しています。
特に、ディンプルキーや電子キーなど高防犯タイプの複製も可能で、賃貸オーナー様や管理会社様からの法人依頼にも柔軟に対応。
千葉県内での現地対応スピードにも定評があります。
「スペアキーを作りたいけど、どこに頼めばいいか分からない」
「管理物件の鍵をまとめて見直したい」―― そんな方は、まずはご相談ください。
経験豊富なスタッフが、鍵の状態やご希望に合わせた最適な方法をご提案いたします。
次の章では、本記事のまとめとして、スペアキー作成を安全・確実に行うための考え方を整理します。
まとめ|“正しく作る”が最大の防犯
一昔前のように「ホームセンターで簡単に作れる」時代は終わり、今ではスペアキー作成も安全性・正確性・管理体制が求められる時代になりました。
防犯性能の高い鍵が増えたことで、「合鍵を作りにくくなった」という不便さを感じるかもしれません。
しかしその背景には、不正複製を防ぎ、入居者や資産を守るための仕組みがあります。
つまり、スペアキーを“正しく作る”ことこそが、最大の防犯対策なのです。
賃貸物件やテナントを管理するオーナーにとって、鍵の管理は単なる備品管理ではなく、信頼と安心を維持するための業務です。
所有する物件が増えるほど、鍵の種類・保管場所・貸与履歴の管理が複雑になりますが、台帳管理やメーカー登録を徹底することで、リスクを最小限に抑え、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、鍵の種類や防犯性能は日々進化しています。
「昔から使っているから」「問題が起きていないから」といった理由で放置せず、定期的に防犯性能の見直しを行うことが、長期的な資産保全にもつながります。
スペアキー作成や鍵交換、防犯診断などを検討されているオーナー様は、鍵の構造やメーカー登録制度に詳しい専門業者へ相談するのが安心です。
レスキューサービス24では一般住宅から賃貸物件・テナント・工場まであらゆる鍵の作成・交換・メンテナンスに対応しています。
特にディンプルキーやマスターキーなど、高防犯タイプの鍵にも対応可能です。
「鍵の管理をしっかり見直したい」
「スペアキーを安全に作りたい」というオーナー様は、まずはお気軽にご相談ください。
現場経験豊富なスタッフが、物件の防犯性やコストバランスを考慮しながら、最適な対策をご提案いたします。
鍵の作成・交換・防犯相談は、レスキューサービス24へ。
千葉県内全域で迅速・丁寧に対応いたします。




