社員が増えたら“鍵”も見直しを!オフィス・店舗向けセキュリティ強化術
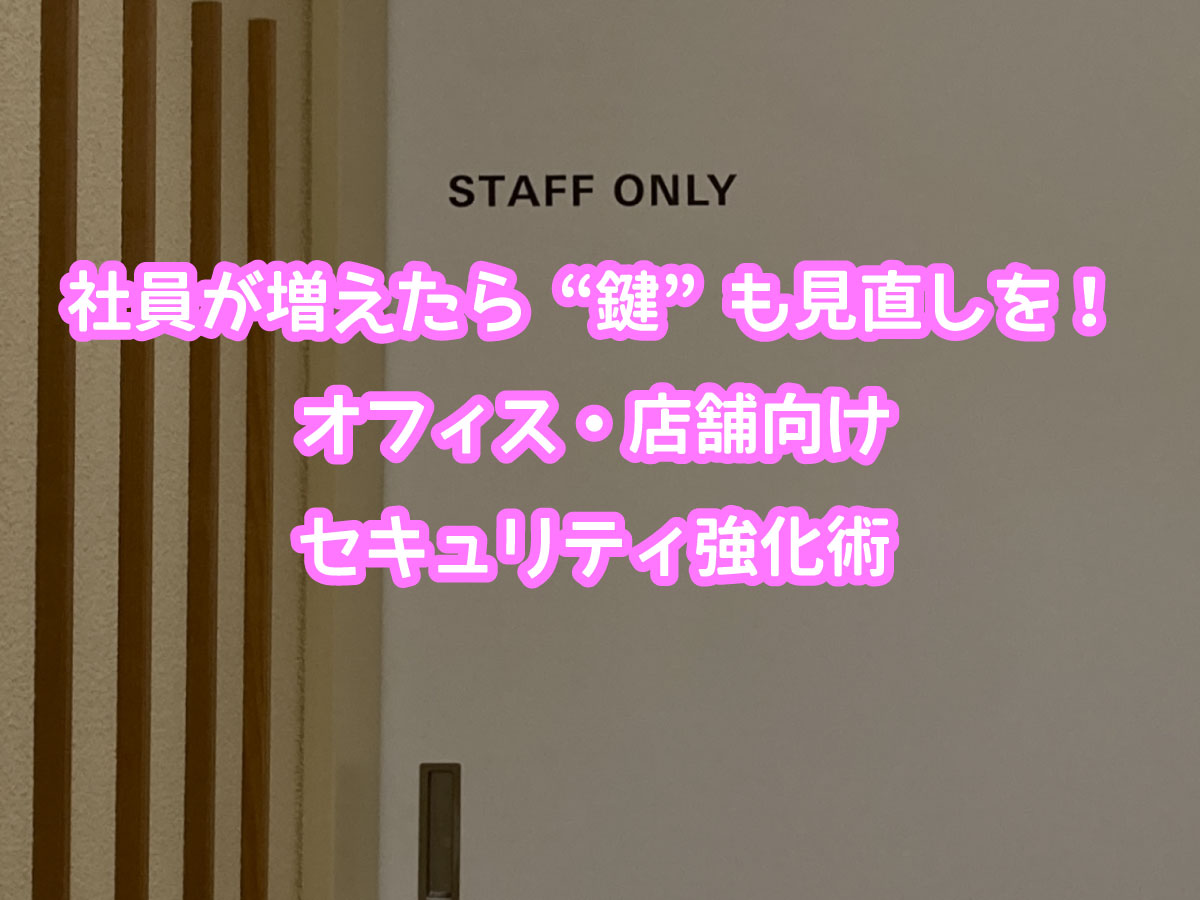
人が増えた分だけ“鍵の悩み”も増えていませんか?
社員の増加や店舗の拡大にともない、「鍵の管理が難しくなってきた」「誰がどの鍵を持っているのかわからない」――そんな悩みを抱えている企業や店舗は少なくありません。
特にシリンダーキー(物理鍵)を使用している場合、人数分の鍵を作るたびに管理の負担と防犯リスクが増していきます。
たとえば、社員の退職時に鍵が返却されなかったり、支店や倉庫で合鍵がどこにあるかわからなくなったり。
こうした“鍵の所在不明”は、業務効率の低下だけでなく、企業の信用や安全性に関わる重大なリスクにつながります。
また、最近ではリモートワーク・シフト勤務・24時間営業など、勤務形態が多様化しています。
その結果、「営業時間外でも入室が必要」「特定のエリアだけアクセスを制限したい」など、従来の鍵管理では対応しきれないニーズも増えています。
このような背景から、今あらためて注目されているのが、カードキーや電子錠、スマートロックなどの“法人向け鍵システム”です。
物理的な鍵を減らし、出入りの履歴を記録・管理できるようにすることで、「安全」「効率」「コスト削減」を同時に実現できます。
この記事では、オフィスや店舗など10名以上が出入りするような職場を中心に、
・なぜ今「鍵の見直し」が必要なのか
・法人・オフィスで起きやすい鍵トラブルの実態
・カードキー・電子錠・スマートロックの特徴と導入メリット
・補助金を使った導入のポイント
について詳しく解説します。
「うちは昔からこの鍵だから」「問題が起きたことはないから」と思っている企業こそ、“管理できているつもり”が最も危険かもしれません。
この記事をきっかけに、御社の鍵管理を一度見直してみませんか?
なぜ今、“法人の鍵管理”が見直されているのか
これまで「鍵の管理」は、単に“出入りのための道具”という位置づけでした。
しかし現在では、企業のセキュリティやコンプライアンスに直結する重要な管理項目として見直されています。
その背景には、次のような社会的・業務的な変化があります。
1. 防犯・情報漏えいへの意識の高まり
不審者の侵入や盗難だけでなく、内部からの情報漏えい・持ち出しも企業にとって深刻なリスクです。
特にオフィスでは、顧客情報や契約書、設計データなど、外部に流出してはならない情報を扱うケースが増えています。
「誰がいつ、どの部屋に入ったか」を把握できる仕組みがなければ、万一のトラブル発生時に原因を特定できません。
そのため近年では、単なる物理的な鍵管理ではなく、入退室履歴をデータで管理する“アクセスコントロール”の導入が進んでいます。
2. 多様な働き方への対応
リモートワーク・フレックスタイム・24時間稼働など、働き方が多様化した今、鍵を「人に依存して管理する仕組み」には限界があります。
たとえば、夜間や休日に作業が必要な社員が鍵を持っていない場合、管理者の立ち会いが必要になり、非効率です。
スマートロックやカードキーなどのシステムを導入すれば、権限を持つ社員だけが必要な時間帯に入室できるよう設定できます。
管理者はアプリや管理画面から即座にアクセス権を変更できるため、柔軟かつ安全な入退室管理が可能になります。
3. 鍵トラブルによる業務停止リスク
鍵の紛失・破損・複製ミスなどは、オフィスや店舗の運営に直接影響します。
「鍵が見つからない」「誰も開けられない」だけで、出社や開店が遅れることも少なくありません。
また、紛失時にシリンダー交換を行うと、費用と手間がかかります。
電子錠やカードキーなら、紛失したカードやIDをシステム上で無効化するだけで済みます。
こうした“復旧の早さ”も、法人向けセキュリティが注目されている理由のひとつです。
4. 法人の信頼性・ブランドイメージへの影響
防犯対策が不十分な企業は、顧客や取引先からの信頼を損なう可能性があります。
オフィスの入口が旧式の鍵のまま、鍵の管理方法も社員任せ……という状況では、「セキュリティ意識が低い会社」という印象を与えかねません。
一方で、スマートロックや入退室管理システムを導入している企業は、「情報管理に強い」「安心して取引できる」と評価されやすくなります。
このように、防犯対策は単なる安全対策にとどまらず、企業の信頼性・ブランディングの一部としても重要視されています。
5. 管理負担を減らす“業務効率化”の一環として
総務や店舗責任者が行う“鍵の受け渡し・回収・記録”は、意外と手間のかかる業務です。
特に複数拠点を持つ企業では、各店舗・事務所ごとに鍵管理のルールが異なり、属人化・管理ミスが起きやすい傾向にあります。
クラウド型の入退室管理やスマートロックを導入することで、鍵情報を一元化し、管理負担を大幅に軽減できます。
人が増えれば増えるほど“アナログ管理”では限界がくる――それが、今法人の鍵管理が見直されている最大の理由です。
次章では、実際にオフィスや店舗で起こりやすい具体的な鍵トラブルと、その原因について詳しく見ていきます。
法人・店舗で起こりやすい“鍵トラブル”5選
社員やスタッフの出入りが多いオフィス・店舗では、「鍵トラブル」が思いがけない業務リスクにつながることがあります。
ここでは、実際に法人で発生しやすい代表的な5つのトラブルを紹介します。
1. 鍵の紛失・返却忘れ
最も多いトラブルが、社員やアルバイトが鍵を紛失したり、退職時に返却し忘れたりするケースです。
特に支店や店舗を複数運営している企業では、どの鍵がどの担当者に渡っているのかを正確に把握できていないことも少なくありません。
鍵が1本でも行方不明になると、不正侵入や内部犯行のリスクが発生します。再発行には時間とコストがかかり、最悪の場合はシリンダーごと交換が必要になることもあります。
2. 鍵の複製・共有による管理不明
「合鍵を作っておいた」「他の社員と共有して使っている」――このような状態も、法人ではよくある問題です。
物理鍵の場合、誰が何本持っているかを管理できないまま運用されているケースが多く、紛失や不正使用が発覚しづらいのが実情です。
特に支店・倉庫・バックヤードなどで合鍵を共有している場合、責任の所在があいまいになりやすく、セキュリティ事故の温床になりかねません。
3. 社員異動・退職時の鍵管理漏れ
部署異動や退職の際、鍵の回収・権限変更を行わずに放置してしまうケースも珍しくありません。
管理ルールが属人的だったり、引き継ぎの中で後回しにされることが原因です。
特に入退室管理が紙やExcelで行われている企業では、更新漏れが頻発します。
結果として退職者が依然として入室可能な状態になっていたり、鍵情報が整理されず「誰も全体を把握できていない」状況に陥ることもあります。
4. 鍵の破損・劣化による開閉不良
長年使用しているシリンダーキーは、内部の摩耗やホコリの蓄積で回りにくくなったり、抜けにくくなったりします。
頻繁に施錠・開錠を行うオフィスや店舗では、毎日の小さなストレスが積み重なり、最終的には鍵の折損などの故障につながることもあります。
また、破損した鍵を無理に使い続けると、シリンダー内部の破損を引き起こし、交換費用がさらに高額になるケースもあります。
5. 誰がいつ出入りしたかわからない
物理的な鍵運用の最大の課題が、「入退室の記録が残らない」という点です。
たとえば、オフィスで金庫や書庫が開けっぱなしになっていたり、倉庫で在庫が減っているといった場合でも、誰が入室したかを特定できません。
セキュリティ事故の発生時、防犯カメラの映像だけでは限界があります。
入退室管理がシステム化されていない企業ほど、「自社内の行動履歴」が残らず、原因追及や再発防止が難しくなります。
このように、鍵トラブルは「物理的な問題」だけでなく、情報管理や組織運営全体に影響を与える可能性があります。
次の章では、こうしたリスクを解消するために導入が進む「鍵管理システム」や「スマートロック」の仕組みを紹介します。
シリンダーキーの限界|“物理管理”では防ぎきれない時代に
長年にわたってオフィスや店舗の出入りを守ってきたシリンダーキー(物理鍵)。
しかし、現在の業務環境やセキュリティ要求に照らすと、その仕組みには限界が見え始めています。
1. 鍵の複製・持ち出しを完全には防げない
シリンダーキーは、金属の形状さえ再現できれば複製が可能です。
メーカーによっては合鍵の作成を制限しているタイプもありますが、完全に防止することはできません。
また、社員やスタッフが意図せずに鍵を持ち出したり、退職後に返却し忘れたりするケースも多く、「誰が今、どの鍵を持っているか」を正確に管理するのは困難です。
人数が増えるほど、鍵の所在管理は煩雑になり、紛失や不正利用のリスクが高まります。
2. 紛失時の対応にコストと時間がかかる
物理鍵を紛失した場合、鍵の再発行やシリンダー交換が必要になります。
特に、1つの鍵で複数の扉を開閉できる“マスターキーシステム”を採用している場合、ひとつの紛失が全館交換につながるケースもあります。
また、交換作業中はそのエリアへの入退室が制限されるため、業務が一時的に止まってしまうリスクもあります。
「防犯のため」とはいえ、時間的・金銭的なロスが発生しやすいのがシリンダーキーの弱点です。
3. 鍵の貸し借り・共有による“管理漏れ”
鍵を複数人で共有して使用する環境では、「誰が最後に使用したのか」がわからなくなることがよくあります。
その結果、開けっぱなし・施錠忘れ・所在不明といったヒューマンエラーが起こりやすくなります。
鍵の貸し借りが頻繁に行われる店舗や工場では、最終的に「誰も責任を取れない管理状態」に陥ってしまうことも少なくありません。
こうした“人任せの運用”こそ、シリンダーキー最大の課題といえるでしょう。
4. 入退室履歴が残らない
物理鍵には「開けた」「閉めた」という履歴を残す機能がありません。
そのため、不審な出入りや内部不正があった場合、事後確認や原因追及が非常に困難になります。
近年は情報漏えいや物品盗難の多くが“内部犯行”によるものとされており、「信頼している社員だから大丈夫」という考え方だけでは通用しません。
入退室の記録をシステムで管理できない限り、組織全体のセキュリティは向上しないのです。
5. 建物の用途や働き方の変化に対応できない
昔ながらの鍵は「一人が一本」を前提に設計されています。
しかし、現代のオフィスや店舗では、パート・アルバイト・委託業者など、出入りする人の属性や時間帯が多様化しています。
そのたびに合鍵を増やしたり、権限を手動で変更したりしていては、管理が追いつきません。
柔軟な働き方を支えるには、やはりデジタル化された入退室管理システムが不可欠です。
これらの課題を背景に、近年ではカードキー・暗証番号錠・スマートロックなど、電子的な鍵への移行が進んでいます。
次章では、それぞれの仕組みと導入メリットを比較しながら紹介していきます。
法人・オフィスにおすすめの“鍵管理システム”とは
「人が増えるほど、鍵の管理が大変になる」――そんな課題を解決するのが、電子化・システム化された“鍵管理システム”です。
最近では、店舗やオフィスだけでなく、工場・倉庫・医療機関・教育施設など、幅広い業種で導入が進んでいます。
1. カードキーシステム|導入実績が多い定番タイプ
ICカードや社員証を使って入退室を行う、最も普及しているシステムです。
カードの登録・削除が簡単にでき、社員の入退室権限を柔軟に設定できます。
紛失した場合でも、カードをシステム上で無効化するだけで対応可能。
物理的なシリンダー交換が不要なため、運用コストを抑えつつ防犯性を高められます。
おすすめの利用環境:オフィス・店舗・医療施設・学校・支店など、出入りが多くIDカード運用がある企業。
2. 暗証番号式電子錠|カード不要で共有がスムーズ
ドアノブやドアの上部に設置し、数字の組み合わせで開閉するタイプです。
物理的な鍵が存在しないため、鍵の受け渡しが不要で、複数人で共有する場所にも適しています。
暗証番号は簡単に変更でき、一時利用コードを発行できるタイプも多く、清掃業者・配送業者・臨時スタッフの対応にも便利です。
ただし、番号の漏えいには注意が必要で、定期的なパスコード更新が推奨されます。
おすすめの利用環境:バックヤード・倉庫・休憩室・共有オフィス・宿泊施設など。
3. スマートロックシステム|アプリと連動した最新型
スマートフォンや専用アプリで開閉できるタイプで、近年急速に導入が進んでいます。
Bluetooth・Wi-Fi・NFCなどの通信機能を活用し、鍵を持たなくても入室できるのが大きな特徴です。
入退室履歴の記録や権限設定、遠隔操作なども可能で、テレワーク・フレックス勤務時代に最適なセキュリティ方式といえます。
特にスマートロックは、既存のドアに後付けできるタイプも多く、リフォームやオフィス改装時の導入が容易です。
おすすめの利用環境:IT企業・スタートアップ・小規模オフィス・個人事業店舗など。
4. 入退室管理システム(アクセスコントロール)|セキュリティを一元管理
ドアやゲート、エレベーターなど複数の入退室ポイントを中央管理システムで一括制御するタイプです。
入室可能な時間帯・人物を細かく設定できるほか、履歴管理・警報連動など高機能な仕組みを備えています。
大規模な企業や複合施設では、他のセキュリティシステム(防犯カメラ、勤怠管理、警備システムなど)と連携させることで、建物全体の安全性をトータルで向上させることができます。
おすすめの利用環境:本社ビル・研究施設・コールセンター・データセンターなど、高セキュリティが求められる環境。
5. 鍵管理ボックス・クラウド型キーキャビネット
「すべてを電子錠に変えられない」という場合には、物理鍵を専用ボックスで管理・記録する方法も有効です。
誰がいつ鍵を取り出し、いつ返却したかを履歴として残すことができるため、従来のシリンダーキーでも安全に運用できます。
最近では、クラウドと連携してスマホやPCから履歴を確認できる製品も増えており、段階的なセキュリティ強化を目指す企業におすすめです。
おすすめの利用環境:工場・倉庫・営業車・社宅・複数物件を管理する不動産業など。
このように、“鍵管理システム”といっても導入目的や規模によって適した方式は異なります。
次章では、それぞれの方式を選ぶ際に押さえておきたい導入前のチェックポイントを解説します。
導入のメリット|“鍵の見える化”で防犯と効率を両立
鍵管理システムの導入は、防犯対策の強化だけでなく、社内の業務効率化やトラブル防止にも大きく貢献します。
ここでは、法人・オフィスが“デジタル鍵管理”へ移行することで得られる代表的なメリットを紹介します。
1. 鍵の所在・履歴が「見える化」される
電子的な鍵管理では、「誰が」「いつ」「どのドアを」開けたかがリアルタイムで記録されます。
従来のように「誰が鍵を持っているかわからない」「開けっぱなしにされた」といった曖昧な状態をなくし、責任の所在を明確にできます。
入退室ログが自動で残ることで、セキュリティ事故が発生した際も原因追及がスムーズ。
防犯カメラとの併用で“人の動きが可視化”され、万一のトラブルにも迅速に対応できます。
2. 紛失リスクを最小化できる
カードキーやスマートロックであれば、紛失時に物理交換が不要です。
システム管理画面から該当ユーザーの鍵情報を削除するだけで、即座にアクセスを無効化できます。
万が一カードやスマホを失くしても、再発行や再設定で対応可能。
鍵交換や再配布にかかる時間的・金銭的コストを大幅に削減できます。
3. 施錠・解錠の自動化で業務を効率化
一定の時間帯に自動施錠を行うタイマー機能や、社員の入退室スケジュールに合わせた開閉設定など、人的な操作を最小限にできる仕組みが整っています。
「閉め忘れ」「開け忘れ」を防ぐだけでなく、店舗の開店・閉店作業を簡略化できます。
また、勤怠管理や入退室ログを連動させることで、業務管理システムの効率化にもつながります。
4. 権限設定で“必要な人だけ”が出入り可能
部署や役職ごとに入室制限を設定できるのも、電子錠の大きなメリットです。
たとえば、経理室・金庫室・サーバールームなど、限られた人しか立ち入れない場所には個別の認証を設定可能です。
シリンダーキーのように「全員が同じ鍵で開けられる」状況を避けることで、情報漏えい・内部不正を防ぐ効果があります。
5. 鍵の受け渡し・管理業務の負担が減る
社員の入退社・部署異動時に行っていた「鍵の貸与・回収・管理」業務をシステム化することで、総務・管理部門の負担を大幅に軽減できます。
カードやアプリで一元管理できるため、紛失時の確認や鍵の所在確認に追われることもありません。
特に人の出入りが多い店舗やコワーキングスペースでは、鍵の受け渡し作業をゼロにできるだけでも大きな業務改善になります。
6. セキュリティ意識が社内全体で高まる
「入退室が記録される」という仕組みがあるだけで、社員のセキュリティ意識は自然と高まります。
物理的な鍵よりも、ルールを“見える形”で運用できるため、組織全体の防犯文化を育てるきっかけにもなります。
このように、鍵管理システムは単なる「鍵の電子化」ではなく、防犯・業務・意識改革のすべてを支える基盤として注目されています。
次章では、導入時に失敗しないための選定ポイントと注意点を解説します。
導入前に確認すべきポイント
鍵管理システムやスマートロックの導入を検討する際は、製品のスペックや価格だけで判断してしまうのは危険です。
オフィスや店舗の規模、業種、運用ルールによって、最適な仕組みや設定方法がまったく異なるためです。
ここでは、導入前に必ず確認しておきたい主要なポイントを紹介します。
1. 建物やドアの構造との適合性
まず確認すべきは、設置するドアの種類や構造に対応しているかどうかです。
引き戸やアルミドア、ガラスドアなど、一部のスマートロックや電子錠は取付不可のタイプもあります。
既存ドアに後付けする場合は、穴開けが不要なタイプを選ぶと、原状回復の必要がなく安心です。
賃貸オフィスやテナントビルの場合は、管理会社の許可も必要になるため、事前に確認しておきましょう。
2. 認証方式の選択
カード、暗証番号、スマートフォン、指紋、顔認証など、認証方法は製品によってさまざまです。
オフィスの運用に合わせて、「利便性」と「安全性」のバランスを考えることが大切です。
- 従業員の入退室管理を重視 → カードキー・暗証番号式
- フレックス勤務や在宅対応 → スマートロック・モバイル連携型
- 高セキュリティエリア → 生体認証+多段階認証タイプ
複数の認証方式を併用できるタイプを選ぶと、柔軟な運用が可能です。
3. 運用コストとメンテナンス
初期費用だけでなく、ランニングコストにも注目しましょう。
クラウド連携型や月額課金制のサービスでは、利用者数や登録端末数に応じて費用が変動します。
また、電池式のスマートロックでは定期的な電池交換が必要です。
メンテナンスを怠ると突然のバッテリー切れで解錠できなくなるケースもあるため、点検スケジュールを運用ルールに組み込むことが大切です。
4. 社内ルールや人の運用に合っているか
どんなに高性能なシステムでも、運用が現場に定着しなければ意味がありません。
導入前に「誰が管理者になるのか」「権限設定はどの部署が行うのか」など、社内ルールを明確にしておく必要があります。
特に人の出入りが多い小売店・飲食店・倉庫などでは、入退室権限の管理を簡単に行えるかどうかが重要なポイントです。
5. 他システムとの連携可否
勤怠管理や防犯カメラ、警備システムなど、既に導入しているシステムとの連携が可能かどうかも確認しましょう。
複数の仕組みがバラバラに運用されていると、情報の重複や管理コストの増加につながります。
最近では、クラウドAPI連携に対応した製品も多く、社内ネットワーク上で一元管理できるようになっています。
6. サポート体制と導入後のフォロー
鍵は毎日使うものだからこそ、トラブル発生時の対応スピードも重要です。
導入後に不具合が起きた際、現地対応や遠隔サポートが可能かどうかを確認しましょう。
また、法人契約の場合は、運用説明や社員教育のサポートを行ってくれる業者を選ぶと安心です。
こうしたポイントを整理した上で、導入目的(防犯・効率化・コスト削減など)を明確にすることで、失敗のないシステム選定が可能になります。
次の章では、こうした電子錠・スマートロック導入を成功させるために、実際に鍵の専門業者へ相談するメリットを解説します。
レスキューサービス24が提案する法人向け防犯ソリューション
レスキューサービス24では、一般住宅だけでなく、オフィス・店舗・工場・倉庫など法人様向けの防犯・鍵管理ソリューションにも多数対応しています。
出入りが多く鍵の管理が難しい現場ほど、“安全性と運用効率”の両立が求められます。当社ではその課題をトータルで解決いたします。
1. 鍵交換・電子錠取付・スマートロック導入に対応
既存のシリンダー錠を防犯性の高いディンプルキーや電子錠に交換するほか、スマートロックやカードリーダー型への変更にも対応可能です。
「後付け型」や「穴あけ不要タイプ」など、建物の構造に合わせた最適な施工方法を提案します。
特に賃貸オフィスや店舗物件では、原状回復が必要になるケースもあるため、施工前に現地確認を行い、最適な防犯プランをご案内します。
2. 建物全体の防犯診断・リスクチェック
防犯は“鍵”だけでは完結しません。
レスキューサービス24では、玄関や通用口だけでなく、勝手口・窓・外構フェンスなど建物全体を診断し、侵入経路となりやすい箇所をプロの視点でチェックします。
「人の出入りが多い倉庫」「夜間営業の店舗」「共有スペースのある事務所」など、それぞれの業態や利用時間に応じたセキュリティレベルの最適化を行います。
3. 鍵管理体制の構築サポート
電子錠の導入だけでなく、鍵の貸出・返却・権限管理のルール設計までサポートします。
運用が現場任せにならないよう、担当者様と一緒に管理台帳や運用マニュアルの整備を行うことで、導入後も安定した運用が可能になります。
また、既存の物理鍵運用から段階的にスマートロックへ移行したい企業様には、混在期間を見越した移行プランも提案いたします。
4. 緊急時対応・アフターサポート体制
鍵が開かない・閉まらないといった突然のトラブルにも24時間365日対応。
鍵交換や修理・解錠など、緊急性の高い案件にもスピーディーに駆けつけます。
また、法人契約では定期点検・メンテナンスのご相談も承っており、導入後の安心サポートを重視しています。
5. 多拠点・チェーン展開企業への対応も可能
複数店舗・複数拠点を運営している企業様向けに、統一規格の鍵管理・施工体制を整えています。
「本社と各支店の鍵を統一したい」「各店舗の開閉時間をシステム化したい」といったご相談にも柔軟に対応します。
エリア拡大や新店舗オープン時にもスムーズに対応できるため、長期的なセキュリティパートナーとしてご利用いただけます。
鍵と防犯のプロフェッショナルとして、レスキューサービス24は「防ぐ・守る・運用する」の3つの観点から企業様をサポートしています。
鍵の交換・電子錠の導入・管理体制の見直しなど、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ|“鍵管理”を変えれば、組織の安全性と生産性が上がる
オフィスや店舗、工場などでの鍵の管理は、防犯の基本でありながら、日々の業務効率にも直結する重要な要素です。
物理的なシリンダーキーのままでは、紛失・管理漏れ・内部不正といったリスクをゼロにすることはできません。
しかし、カードキーやスマートロックなどのデジタル鍵システムを導入すれば、「誰が・いつ・どこを」開閉したかを“見える化”し、責任の所在を明確にできます。
これは単なる防犯強化にとどまらず、業務フローの改善・社員の意識改革・管理コスト削減にもつながる大きな変革です。
社員数や拠点が増えるほど、鍵のトラブルは複雑化します。
逆に言えば、鍵管理を見直すことこそが、企業の信頼性と安全性を底上げする第一歩です。
レスキューサービス24では、法人・店舗向けの防犯診断から鍵交換・電子錠導入・運用サポートまで一貫して対応しています。
「うちもそろそろ見直したほうがいいかも」と思ったタイミングが、まさに始めどきです。
企業の鍵管理を“守るだけ”から“活かす”へ。
安全性と生産性を両立させるための最適なソリューションを、レスキューサービス24がご提案いたします。




